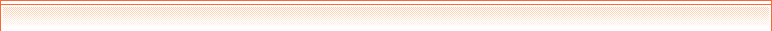こんばんは!昨日、下関市で第4回目の『古代史シンポジウム』が開催され、わが考古学部も参加させて頂きました。
これまで、第1回目から第3回目までのテーマは、弥生時代の日韓交流についてでしたが、今年は『弥生時代のクロスロード』と題し、日本と大陸との交流を支えた「道」に焦点があてられ、その中でも、日韓交流の中継地点となった「壱岐・対馬」の弥生時代について、地理的事項や古文書(『魏志倭人伝』)の記述、地理的状況を背景に、講演・討論会がありました。
「壱岐・対馬」と、一括りにされがちな地域ですが、それぞれの特徴を細かく見ると、「対馬には岩場が多く、農耕に適した土地柄ではない一方、壱岐には平野があり、十分ではないが農耕可能な土地であった」などの相違点がある、とのことでした。
また、両者の関係は、その地理的条件から「朝鮮半島に近い対馬が、原材料を輸入し、供給できる「問屋」に、日本列島(特に奴国)に近い壱岐が、製品を供給できる「デパート」であった」というユニークなご指摘もありました。
また、「壱岐・対馬の弥生人」については、3タイプに分類される弥生人の中でも、壱岐・対馬のそれは、面長で、鼻根部が低く、高身長な「北部九州・山口タイプの弥生人(渡来系弥生人)」に分類され、大陸との関係が示唆される、とのことでした。(なお、壱岐南部からは縄文系弥生人の遺骨が発見されており、彼らが海上移動の際、日本列島の水先案内人としての役割を担っていたのではと考えられているようです。)
いずれにせよ、両者とも単なる中継地点ではなく、上記のような特徴をそれぞれ持ち、小規模ながら、特定の集団(ただし統一的・国家的な存在では無い)を形成していたことが言えるようです。
、、、おっと、つい長くなってしまいました(;´∀`)
という感じで、普段、触れる機会の無い「壱岐・対馬の弥生時代」について学ぶ機会を得ることができ、考古学、ひいては古代史への興味・関心が高まりました!
(ちなみに、今回のシンポジウムの記事が9月3日(金)付けの山口新聞に掲載されておりますので、良ければそちらもご覧ください<(_ _)>)
来年も開催されるそうなので、楽しみです✨ 良ければ、皆様もご参加ください!
それでは失礼します。
PR